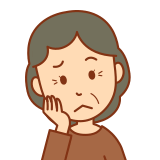
足が攣ったー!
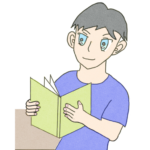
大丈夫ですか?
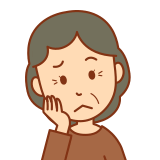
毎回起きる時に攣るのは、何でだろう?
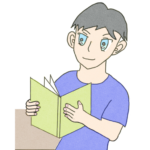
えーと、脱水でしょうか?

脱水の可能性もあるね!
でも毎回って所が気になるよ!評価してみよう!
「朝起きた時に足がつってしまう…」
そんな経験が続いている方はいませんか?
一般的に脱水が原因といわれますが、毎日のように起き上がるタイミングで足が攣る場合、別の要因が隠れている可能性があります。
理学療法士の視点から、原因の見極め方と改善ポイントをわかりやすくお伝えします。
足が攣る部位とタイミングを確認する
なぜ足が攣るのかを評価する|筋緊張や起き上がり動作に注目
足が攣る原因に対するリハビリアプローチと再発予防
足が攣る部位とタイミングを確認する
ハナさんの既往歴
腰椎圧迫骨折
仙骨骨折
訴えとして起き上がりの際に、右足底が攣ります。
足底全体が攣っている感覚との事。

寝る時は大腿〜下腿にかけて、クッションを入れています。
足が高い方が気持ちが良く、この姿勢にしているとの事。

起き上がる時は、クッションに足を置いたまま長座位になります。

長座位になってから左、右と下肢をベッドから下ろします。

長座位になる時に右足底が攣るとの事。
右足底全体が攣るような感覚
長座位になったタイミングで生じる
なぜ足が攣るのかを評価する|筋緊張や起き上がり動作に注目
ハナさんはクッションに両下肢を乗せたまま、左肘を支点とし長座位になります。

下肢を挙上したままで起き上がりを行う為、腹直筋・腹横筋・腹斜筋には負担がかかります。
起き上がりを行う為には、下肢へ体重を移行させる必要があります。
体重を移行させる事で、両下肢が土台となり起き上がれます。

しかし両下肢が挙上しており、体重を両下肢に移行する事が困難です。

その為体幹を屈曲する為に必要な、土台を作りにくくなります。
この時のハナさんのリアクションとして、右足関節が底屈しています。

底屈すると右下肢を伸展方向に誘導でき、長さを増す事ができます。
つまりレバーアームを増加させられます。
更に重力を味方につける事ができます。
レバーアーム全体に重力がかかりますので、起き上がりの土台を作る為に、足関節が底屈する方が都合が良いです。

しかしその分右下肢に大きな負荷が求められます。
その結果、末端の右足底が攣ってしまったと考えます。
下肢を挙上したままの起き上がりは難易度が高い
起き上がりの際に右足関節を底屈させる事で、動作を可能している
右下肢にかかる負担が増加し足底が攣っている
足が攣る原因に対するリハビリアプローチと再発予防
クッションを除去するのがてっとり早いのですが、本人にとってお気に入りの寝方でした。
その為クッションを取るのは難しく、代替案を提案する必要がありました。
そこで両股関節を屈曲しながら、ベッドの左側から下垂してもらうように提案しました。

更に両下肢を下垂させた際に、その勢いのまま左肘に体重を乗せて起きてもらいます。
この動作によって症状が改善しました。

右下肢の負担を軽減する方法を提案する事で、症状を予防する事が出来ました。
両下肢の下垂と同時に、左肘に体重を乗せるタイミングが難しい為、適宜タイミングを伝える必要がありました。
下肢のレバーアームを減少させる起き上がりを提案する
まとめ

今回は起き上がる際に、足が攣ってしまう方への対応を解説しました。
治療の手順は、以下の通りです。
足が攣る部位とタイミングを確認する
なぜ足が攣るのかを評価する|筋緊張や起き上がり動作に注目
足が攣る原因に対するリハビリアプローチと再発予防
今回は起き上がりの負担により、足底が攣っていました。
しかし原因が分からないと、何かの病気かもと焦ってしまう方もおられます。
特別な事をしなくても、動作の提案で解決できる問題もあります。
筆者も引き続き、動作観察を怠らないようにしていきたいです。
おすすめ書籍
動作分析を深めるうえで、着眼点や視点の広がりを得られた一冊がありますので、ご紹介いたします。
臨床や実習の中で、「どこに注目すればよいか」が見えにくいときに、自分にとって大きなヒントになった本です。
ご興味のある方は、一度手に取ってみてもよいかもしれません。
▼書籍リンクはこちら
※本記事で紹介した書籍は、筆者の個人的な感想・経験に基づくものであり、すべての方に同様の理解や効果を保証するものではありません。
足がつる原因には、筋緊張や起き上がり動作の影響が隠れていることがあります。
以下の記事もあわせて読むことで、症状への理解と対応の幅が広がります。
✅ 起きると腰が痛いのはなぜ?理学療法士が原因と改善方法を解説【CASE2】
✅ 夜中に太ももが痙攣するのはなぜ?筋緊張のリスクと緩和策を理学療法士が解説【CASE18】
✅ トイレまで我慢できない原因は?便失禁を防ぐためのリハビリ方法を理学療法士が解説【CASE16】
最後に
この記事を参考にされる際は、目の前の患者さんに紹介した評価・治療が適応できるか判断していただいた上で使用して頂ければ幸いです。
患者さん一人一人、疾患、既往歴、身体的特徴等異なります。
そのため、今回ご紹介した治療は万人に対して、再現性を担保できるものではありません。
それらを踏まえた上で参考にして頂ければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
以上、ユウセイでした。

noteでは、臨床での学びや日常で感じたことも発信しています。ぜひ気軽にご覧ください。

Instagramで最新記事のお知らせをしています!是非フォローをよろしくお願いします。



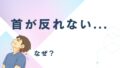

コメント