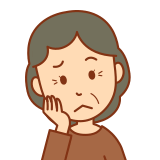
歩くと右足が出しにくい!
筋力がないのかしら?

右足に問題がありそうですかね?
筋力低下とか!

それが一概にそうともいえない
一緒に評価してみよう
歩行中に足が思うように前に出ない…。
そんな悩みを抱えている方は少なくありません。
一歩が出にくいだけで、移動のたびにストレスや不安を感じてしまいます。
しかし、動きのポイントを整理しながら向き合うことで、足が前に出やすくなるケースがあります。
今回は、すり足になってしまう方への 動作の見方・ケアの考え方 を、理学療法士としての臨床経験をもとにご紹介します。
すり足歩行にみられる問題点を評価する
動作や姿勢から見える特徴を確認する
今回のケースでは
左変形性股関節症術後(左人工股関節全置換術後) の方で、
- 右足がすり足になりやすい
- 前に転びそうな感じがする
という訴えがありました。
このようなときは、
「すり足そのもの」だけでなく、体重がどの下肢に乗りやすいか も重要なポイントになります。
体重移動の偏りをチェックする
左右の支持性を簡便に評価する方法
簡単な確認方法として、左右の踵を交互に軽く上げてもらいます。
- 踵を上げたときに重心が大きく移動する側
→ 支持側の下肢には体重が乗りにくい傾向がある
今回の方では、
右踵をあげたときに重心移動が大きい=右に体重が偏りやすい
ことが分かりました。
右に偏ることで左足への体重移動が不足し、
結果として 右脚の振り出しが難しくなっている可能性 が考えられます。
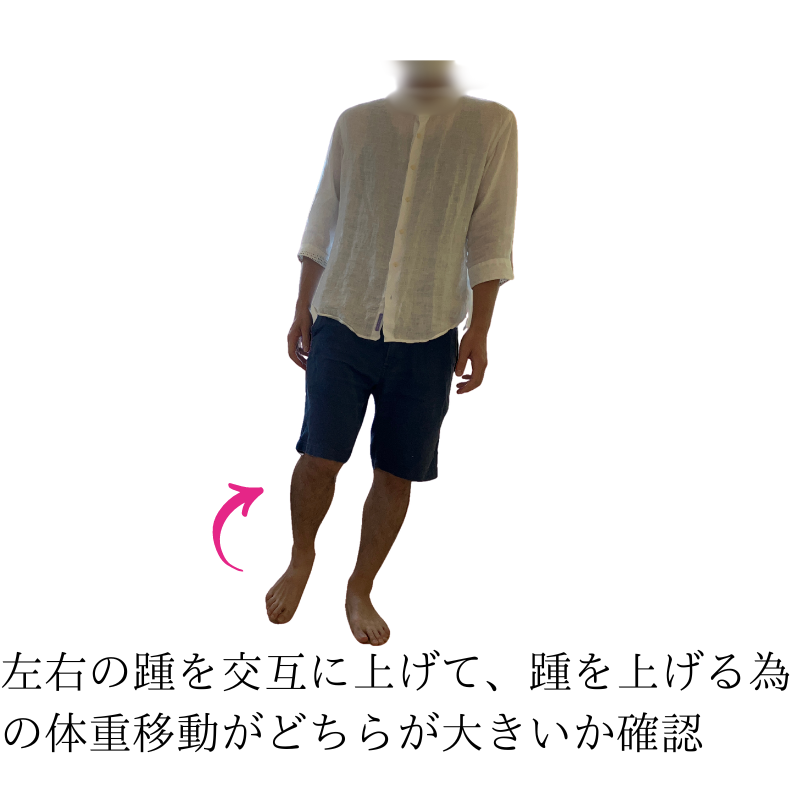
左右の足底感覚を確認する
足底3点(母趾球・小趾球・踵)の認識を評価する
足底の感覚も動作に影響します。
確認したところ、
右と比べて 左の母趾球・小趾球・踵の感覚が分かりにくい とのことでした。
- 左足底の感覚が弱い
- 左下肢に体重が乗りにくい
この2つが揃うと、右足を軽くして前に出すタイミングが生まれにくくなる と考えられます。
すり足に対するケアの考え方
問題点
左足底の感覚低下の可能性がある
左下肢に体重が乗りにくい可能性がある
足底感覚を促すアプローチのポイント
足底の感覚を認識しやすくするため、
以下の 3 点へ刺激を与えます。
皮膚が弱い方には指で刺激します。
- 母趾球
- 小趾球
- 踵
タオルでこすったり、指で触れて刺激を入れる方法などがあります。

この3点の感覚を捉えられると、
“どこに体重が乗っているか” が分かりやすくなります。
体幹前傾で足裏に体重を乗せる意識づくり
感覚を促したあとは、体幹を前傾して
足裏の3点に体重が乗る感覚 をつかんでもらいます。
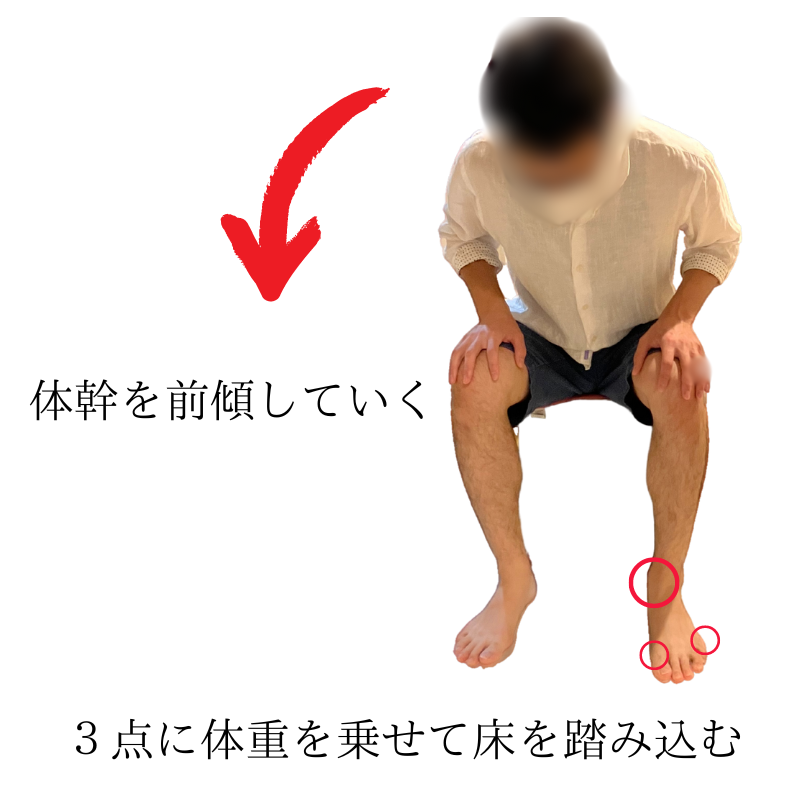
重心移動を改善するためのポイント
左右方向の重心移動を感じる練習
骨盤を壁や目標物に近づけるようにして、
左右方向へ体重をゆっくり移動していきます。
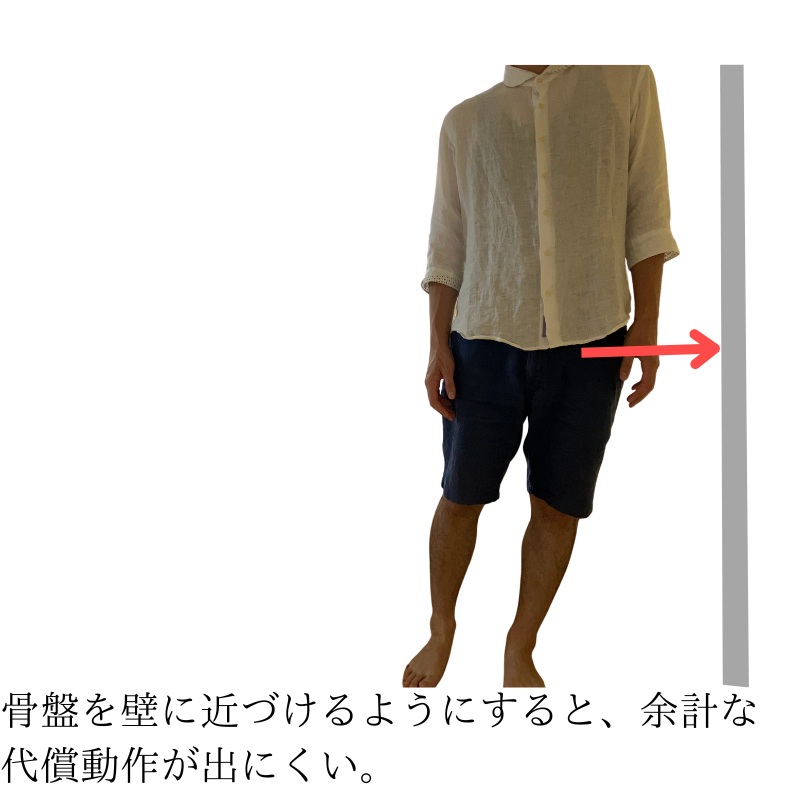
左足に体重が乗る感覚がわかると、
右足の重さが軽くなっていくのを感じられる場合があります。

恐怖心があれば、支持物を触りながらでも良いよ
踵から前足部への体重移動を捉える練習
先程はほぼ真横に体重移動を行ってもらい、
左下肢に体重を感じてもらいました。
立脚中期〜後期では、
体重は「踵 → 前足部 → 母趾」という流れで移動することが多いです。
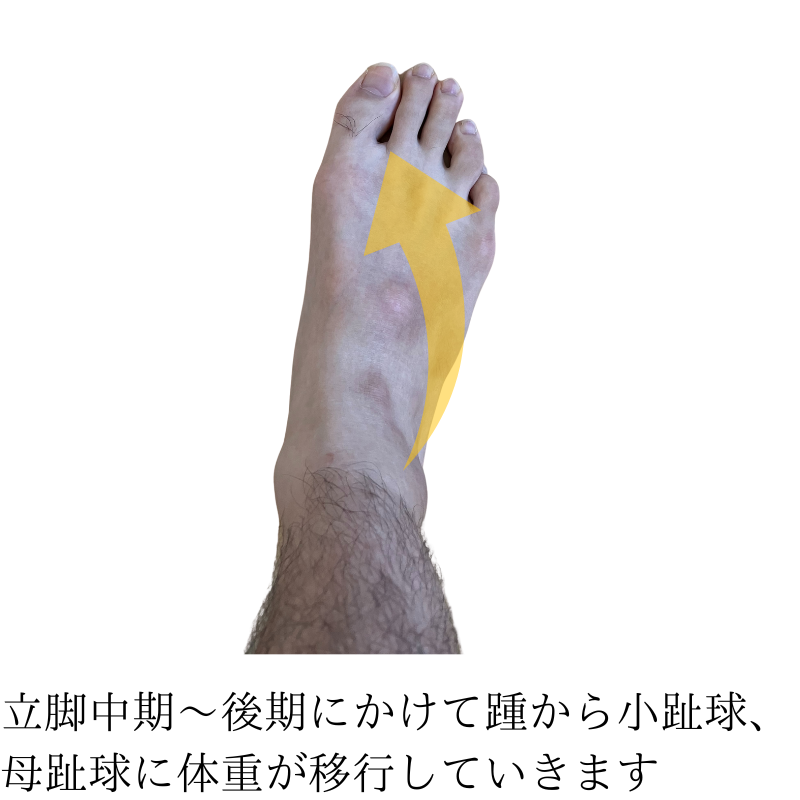
そこで、壁に背中や骨盤を近づけたり離したりして、
踵から前足部へ移動する重心の流れ を感じてもらいました。
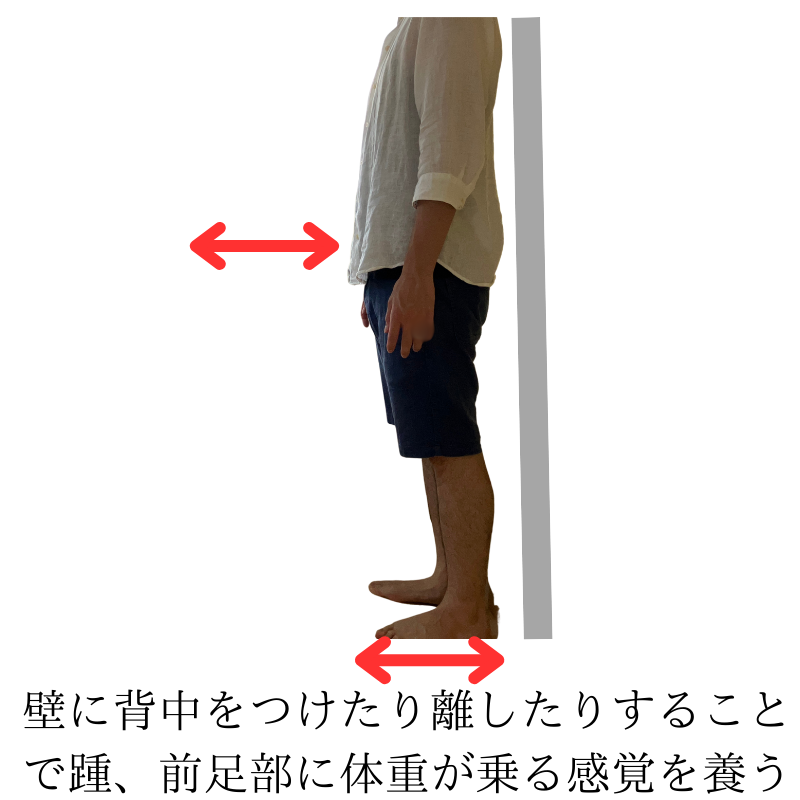

立脚中期〜後期は体重が前方に移動する
その感覚に気づくための訓練だね
ステップ動作につなげるための練習
足が“軽くなる瞬間”をとらえて一歩を出す
前足部へ体重が移動すると、反対側の踵が自然と浮いてきます。
右踵が浮いたら、そのまま軽くステップ。
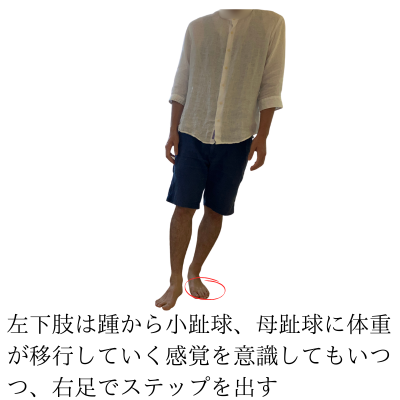
この動作を繰り返すことで、
「右足が軽くなる → 前に出せる」
というタイミングがつかみやすくなりました。
そのため支持物が近くにある状態で、
このステップ訓練を自主練習としました。
歩行中にすり足が出そうになった場合は、立ち止まり
重心移動を意識してもらいました。
徐々に歩行にも変化が出て、
数週間後には「すり足が気になりにくくなった」との声がありました。
ハナさんは、
左足底の感覚低下の可能性がありました
左下肢に体重が乗りにくい可能性がありました
上記のケアとして、足底の感覚入力を行い、左下肢で体重を支える認識を持ってもらうことを意識しました。
また体重移動によって右下肢が軽くなる感覚を養い、右下肢を振り出すタイミングを掴んでもらいました。
以上のことで右下肢が振り出しやすくなったと考えられます。

最初は軽くなったら振り出してもらう
慣れたら無意識に歩いてもらうよ

右足が軽くなる感じが分かったわ
てっきり右足が悪いと思ってた
まとめ

今回のケースで整理したケアの手順
- 左足底(母趾球・小趾球・踵)の感覚低下と、左下肢に体重が乗りにくい可能性を整理する
- 足底に軽い刺激を入れて感覚を促通し、左下肢に体重が乗りやすい姿勢に整える
- 左へ体重が乗ったときの「右下肢が軽くなる感覚」をつかんでもらう
- 左右の体重移動を繰り返し、右下肢が軽くなったタイミングで小さくステップする
- 歩行中にすり足が出そうなら一度止まり、体重移動を再確認する
- 足底感覚の改善と体重移動の習得により、右下肢が振り出しやすくなり、すり足が軽減した
すり足になると、「足が悪いのでは?」と考えがちですが、
実際には 体重移動や足裏の感覚 が大きく関係する場合があります。
動作の背景を丁寧に見ていくことで、
歩きやすさにつながるヒントが得られるはずです。
🍀もっと深くを学びたい方へ
noteでは、学生・若手セラピストの方に向けて
臨床で使える「転倒を遠ざけるための評価とバランス改善」の考え方をまとめています。
現場での観察視点や、リスク低下につながるリハビリアプローチを
図解を交えながら詳しく解説しています。
🔗 関連記事はこちらもおすすめです
✅ 歩行時の殿部のだるさ・痛みの原因は?理学療法士が徹底解説【CASE20】
足が出にくい背景には、股関節まわりの筋機能や殿部の負担が関係しているケースもあります。立脚期の観察や評価視点を深めたい方におすすめです。
✅ ふくらはぎが痛くて歩けないのはなぜ?原因と改善方法を理学療法士が解説【CASE13】
歩行中のふくらはぎ痛も、重心の乗り方や足部の使い方が関係することがあります。評価のポイントと、臨床で使えるアプローチを紹介した記事です。
✅ 片足立ちができるようになりたい!体のバランスを整えるコツをわかりやすく解説
右足が出にくい原因のひとつに、片脚支持の不安定さがあります。バランスを整えることで歩行の安定性が向上します。
最後に(免責)
本記事は一般的な情報提供を目的としています。
目の前の患者さんへの適応可否は、各自の評価と専門職としての判断に基づいて実施してください。
患者さん一人ひとりで疾患・既往・身体特性が異なるため、記載内容がすべての方に同様の効果をもたらすとは限りません。
本記事を参考にして生じた損害等について、筆者は一切の責任を負いかねます。
あらかじめご了承ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
以上、ユウセイでした。

noteでは、臨床での学びや日常で感じたことも発信しています。ぜひ気軽にご覧ください。

Instagramで最新記事のお知らせをしています!是非フォローをよろしくお願いします。


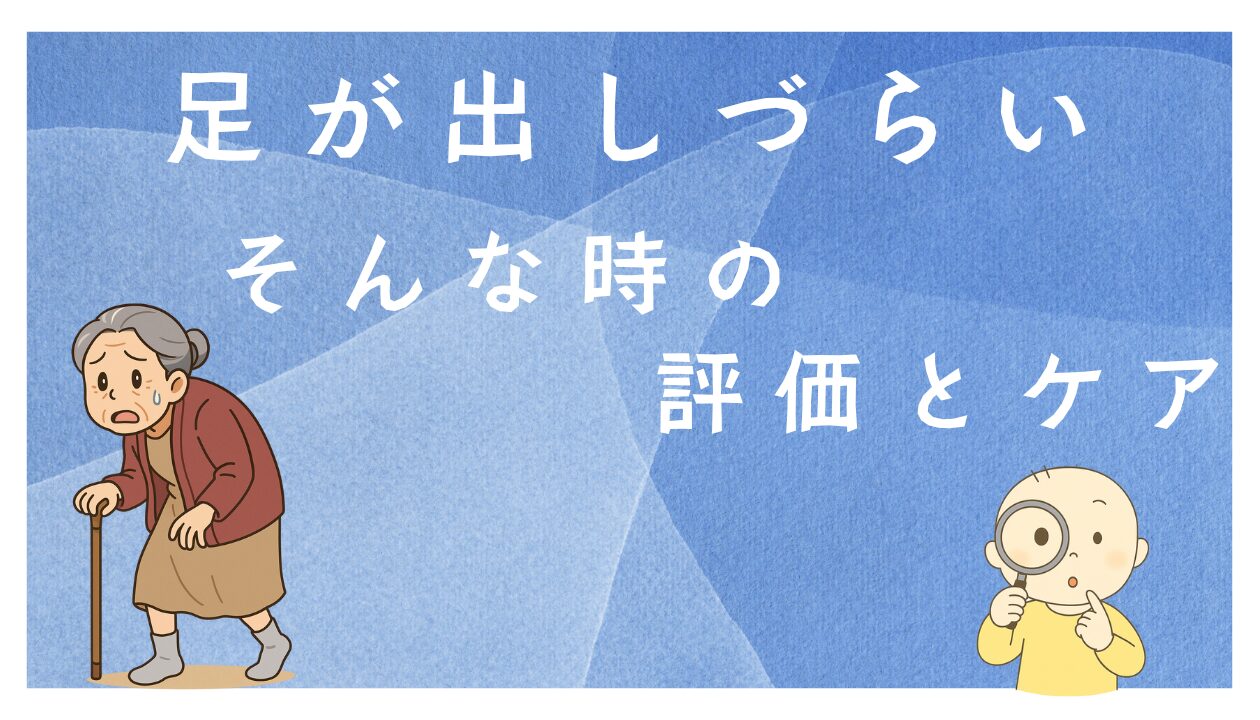
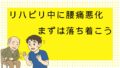
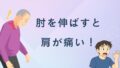
コメント